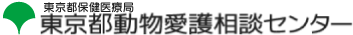ペットロスを考える
コンパニオンアニマル
人は、動物を食料や日用品の原材料として活用してきた時代を経て、犬は狩りのパートナーや番犬、猫はネズミ捕りなどの使役動物として生活に役立ててきました。欧米を中心に、家庭で暮らしている「ペット(愛玩動物)」は、「コンパニオンアニマル(伴侶動物)」と呼ばれるようになってきました。このことからもわかるように、犬や猫などのペットは単なる動物ではなく、人と人生を共にするパートナー、仲間、友として認識されるようになってきました。これらの変遷からわかるように、動物から得られる恩恵は、実質的なものから、関係性から得られるものに変化してきました。ただし、日本では「コンパニオンアニマル」の呼称はあまり用いられないため、本コラムでは同じ意味で「ペット」を使用します。
近年、ペットは家族の一員として共に暮らしています。嬉しいときは共に喜び、悲しいときは傍らに寄り添ってくれています。ペットは家族といえども不思議な家族です。ある人にとっては子どものような、ある人にとっては孫のような、お子さんにとってはきょうだいのような存在。変幻自在な家族といってもいいかもしれません。

お子さんのいるあるご家庭で、ラブラドール・レトリバーのラブちゃん(仮名)を飼っていました。ラブちゃんと一緒に遊んだり、おもちゃの取り合いをしたり、一人っ子だったその子とは本当のきょうだいのように育ちました。ときにはきょうだい葛藤のような経験もします。そのような過程を経て、成長するとともに、ラブちゃんを守ってあげよう、ケアしてあげようという意識が芽生えていったそうです。また、落ち込んだときにラブちゃんを抱え込んでじっと座っていたといいます。子どもは言語の発達が途上なので、自分の気持ちや考えを言葉にすることが難しいときがあります。そんなとき、ペットは言葉を介さずに寄り添い受け入れてくれるのです。子どもは、ペットとの愛情と優しさに満ちたやりとりから、無条件に受け入れられていると感じます。このようにペットはカウンセラーのような存在にもなりえます。子どもにとっては力強いサポーターなのです。
適正な飼養、予防獣医療の充実、栄養価の高いフードの普及で、ペットの寿命は延びてきました。ペットフード協会(2024)の全国犬猫飼育実態調査によれば、犬の平均寿命は14.90歳、猫は15.92歳と報告されています。今では18歳の犬、20歳の猫も珍しくありません。たとえば、小学校に入ったときに子犬や子猫を迎えたとすると、25歳ごろまで暮らすことになります。中学や高校、大学への進学、就職、結婚、様々な節目となる大切なライフイベントも一緒に経験します。ペットの長寿命化は、共に生きる大切な時間を長くしてくれたのです。また、数十年前までは犬や猫のペットのほとんどが外で飼われていましたが、現在では多くが家の中で飼育されています。家の中で暮らすことによって、ペットは主体的に自由意志で飼い主と関わることができるようになりました。人とペットの関係が親密になり、家族の一員と認識されてきたのは、これらの要因が関与していると考えられます。
ペットといると癒される、楽しい、家庭が和やかになる、子どもの情操教育になる、孤独感が軽減される、生活リズムが整う、運動不足が解消される、必要とされていると感じるなど、私達はペットから多くの恩恵を授かっています。そして、人と動物の関係学の分野の研究者や実践者が、ペットは無条件の愛情を与えてくれる存在だといいます。役割や肩書、持っているものの条件によって判断することなく、あるがままに受け入れてくれ、愛してくれるのです。
多くの人が、ペットは子どものような存在であるといいます。行動やしぐさ、可愛らしさ、あるいは世話を必要とするので、そう捉えやすいのでしょう。人間の子どもの場合は、時とともに成長し、やがて巣立っていきます。しかし、ペットは、いつまでも変わらず(本当は加齢しているのですが)、いつまでも傍にいてくれます。ところが、子どものような存在なので自分よりも先に逝ってしまうはずはないと漠然と信じていたにもかかわらず、ペットは自分よりも早く亡くなってしまうという現実に遭遇します。