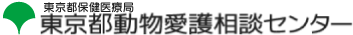ペットロスを考える
ペットロスとは
ペットロスは、特別な人が陥る症候群と誤解されがちですが、ペットに愛情を注いでいる誰しもが経験することなのです。大切な者やペットを失った人は、同じような悲しみの心のプロセスをたどるといわれています。その悲しみや苦痛から抜け出すためには、多くのエネルギーを費やし、十分な時間が必要となります。ペットに対して愛情を注いでいるにもかかわらず、その対象が目の前からいなくなってしまう。ペットが亡くなったからとはいえ、ペットへの思慕は消えません。受け取る相手のいない行き場を失った思慕の情はそこに留まり噴出して悲しみを深くします。そのような思いを一つ一つ解放していくことは、とても苦しい作業になります。大切な対象を喪失した事実を受け入れ、悲しみから回復していく長い道のりの始まりです。
ペットロスとは、愛着対象であるペットを死別や別離で失う対象喪失の一つであり、それに伴う一連の苦痛に満ちた深い悲しみ、悲嘆(グリーフ)の心理過程の総称のことをいいます。悲嘆は、ペットを失うかもしれないと意識したときからも始まるといわれています。ペットを失う原因には、死別と別離があります。死別には、老衰、病死、安楽死、事故死などがあります。ただし、病気と一概にいっても原因や状況、その看護や介護期間も異なります。別離には、飼い主の身体上や生活の事情でやむを得ず手放す、ペットが行方不明になるなどがあります。これらの喪失原因がペットロスに伴う悲嘆の長さや強さに影響するといわれています。

予期できない別離、突然死などの突然の別れは周囲の注意が必要です。心の準備ができておらず、その悲しみから抜け出すことが難しいとされています。たとえば、ペットの失踪や災害などで生き別れた場合、そのペットが生きているか亡くなっているかが分からないため、ある家族はお葬式をしたいというが、別の家族はどこかに生きているはずだから待ちたいという、このように事実が不明慮なため家族間で意見が異なり、本来は喪失の悲しみを支え合うはずが、そのサポート源が機能しないという問題が発生するのです。
ペットロスに伴う反応には次のようなものがあるといわれています。泣く、眠れない、食欲がなくなる、頭痛、腹痛、喉がつまる、悲しい、落ち込む、怒りがわく、自分を責める、憂鬱 になる、無気力になる、孤独を感じる、一人になりたいと思う、誰とも会いたくなくなる、頭が混乱する、集中できないなどです。これらのように、心身を問わず、様々な側面にペットを失ったことによる悲しみの症状が現れます。
喪失して間もないころは、ネガティブな感情が渦巻き、それが心の大部分を占めポジティブな感情を覆い隠します。悲しい、苦しい、痛い、自分が許せない、一人ぼっちと感じる、ペットを取り戻したい、納得がいかない、もっともっとしてあげられればよかった、これらのような感情や後悔が押し寄せてきます。また、ペットとのコミュニケーションの多くが、抱っこする、ハグする、撫でるなどのスキンシップです。したがって、「触れられない」ということが、心理的な悲しみに加え、身体で感じる喪失感をもたらすと考えられます。
家族間でもペットを失った悲しみの度合いに温度差があり、理解が得られず孤立してしまう場合もあります。また、ある家族は次のペットを迎えたいと希望しているが、別の家族はもう二度と飼いたくないと思っている、このように次のペットを迎えることに対する意見の食い違いがある場合もあるのです。
一方、「動物が死んだくらいで」や、「また同じ犬種や猫種を飼えばいい」という、心無い言葉や態度が当事者たちを苦しめます。ペットロスは、喪失対象が動物であるという理由で軽視される傾向があります。そのような世間の非理解が悲しみに追い討ちをかけます。そうすると、誰にも言えない、この気持ちを分かってもらえない、話したとしても理解されないと悩んでしまい、悲しみを押し込め孤立してしまいます。また、「こんなに悲しいなんて私はおかしいんじゃないか」、「仕事や家事も手につかないほど落ち込む自分は変かもしれない」と自分でも悲しみを認めづらく悩んでしまう場合もあります。
ペットロスは、公に認められにくい悲しみの一つといわれています。前述のように、当事者が悲しみを経験しているにもかかわらず、社会や世間に受け入れられにくいため、周囲のサポートを得るのが難しいという課題があるのです。
前のページは:コンパニオンアニマル
次のページは:ペットロスの悲嘆(グリーフ)の心理過程