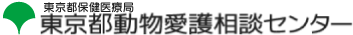ペットロスを考える
ペットロスの悲嘆(グリーフ)の心理過程
ペットを失った時、ショックを受けて呆然とする、咄嗟に信じられないと思うでしょう。ペットを喪失した事実を受け入れがたいのは、衝撃から心を守るための正常な反応だといわれています。しかし、喪失の事実を受け入れなければ、乗りこえる、回復する方向には進めないのです。一方で、ペットを亡くした事実を受け入れることは、断ち切られた絆に直面することになります。そうすると、ペットの不在を強く意識させられます。同時に、悲しみ、もしくは自分を責める気持ち、行き場のない怒りなどの感情が湧いてきます。

お子さんを亡くした場合は、他の家族を亡くしたときよりも自分を責める気持ちが強く現れるといわれています。庇護しなければならない子どもを守れなかったことに対する罪悪感を持つのです。多くの人がペットは子どものような存在であると捉えています。したがって、子どものようなペットを、守ってやれなかった、病気に気づいてあげられなかった、助けてあげられなかったと、強く自己を責め、罪悪感に苛まれるのです。しかし、自分を責める気持ちは愛情と責任感の裏返しともいえるのです。
これらの怒りや自責感は、抑うつ徴候と関連しているといわれます。抑うつ状態とは、気分が落ち込み、憂鬱 になり、何もやる気がなくなってしまうことです。また、悲しみ、痛み、落胆、絶望などの感情、体調が不調になる、うまく考えることができない、周りの人とうまくコミュニケーションがとれない、なんとか取り戻したいと頭で考えるなどを多かれ少なかれ経験するといわれています。
日常生活を続けるなかで、悲しみや痛みに向き合い、ペットがいない生活に慣れていき、ある時は悲しみ、ある時はペットとの続いていく絆に気づく、生活に適応していく、それらを行ったり来たり揺らぎながら回復に向かいます。
多くの人が時間はかかりますが、自身にもともと備わった力で、周囲のサポートを得て、徐々にペットを失った悲しみを乗りこえ、回復していきます。ここでいうペットロスを乗りこえる、回復するというのはどのような状態なのでしょうか。それは、ペットのことを思い出すと悲しみや苦痛に圧倒されて生活に支障がある状態から脱することであり、自分なりに折り合いをつけられている、ペットとの続く絆を意識できる、再び関係を結び直していけることだと思います。言い換えれば、ペットのことを思い出した時に悲しい、苦しい、辛い、もっとしてあげられれば良かったなどの後悔、このようなネガティブな感情が収まっていき、ペットとのあたたかい思い出や楽しい思い出が多くを占めるようになり、ペットは自分の家に来て幸せだったと思える、感謝の気持ちが満ち溢れ、ペットが傍にいる感覚などが悲しみを覆い包んでくれることだと思います。
愛情を注いでいるペットを喪失すれば悲しいのは当然のことです。ペットのことを忘れなくてもいいですし、ペットに関連する物をむりやり片付けなくてもいいのです。また、次のペットを迎えるか、いつ迎えるのかは、個々人のペースでいいのです。
一方、お別れのセレモニーやメモリアル、葬祭(葬儀、火葬、霊園、供養)など、家族の希望に合ったお別れをすることも回復に向かうことに有効であると考えられます。それらは、気持ちに区切りや整理がつきやすくなる、信頼できる人々と悲しみを分かち合う、ペットのためにやってあげられることがあるという点で、サポートになると考えられるからです。