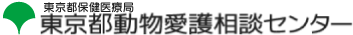ペットロスを考える
子どもとペットロス
ペット飼育が子どもの成長に良い影響を与えることは多くの研究が示しています。ただし、子どもとペットが愛着を築いていることが前提になります。愛情を注いでいるからこそ、そのペットの立場になって考え、気持ちと欲求を推し量り、一生懸命に世話をし、途中で投げ出さないのです。そのような過程を経ることで、子どもの自尊心、忍耐力、共感性、役割取得の能力、観察力、責任感、生命尊重の心を養うことにつながるのです。

どの年代もペットロスのサポートは必要ですが、特に子どもの場合は周囲の大人たちの態度が鍵を握ります。ペットを失ったときには、大人は子どもと一緒に最期のお別れをすることが望ましいと考えられます。時折、大人たちは、子どもがかわいそうだ、死に遭遇した子どもに対応できないなどの理由で、子どもたちから死を遠ざけることがあります。しかし、子どもが分かる範囲で亡くなった理由について伝えないと、なぜいなくなったのかの疑問が残ります。ペットが死んだのは自分のせいかもしれないと罪悪感を持つこともあるので配慮が必要です。子どもがペットの死に直接関係の無いときでも自分を責める場合があります。大人は、子どもが自身を責める気持ちを解きほぐし、その子どもの責任ではないことを伝えてあげてください。ペットとの大切な思い出を語り合うのも回復へのサポートになると考えられます。
保護者自身がペットを失って悲しいからといって、子どもがペットの死について話すことを避けてしまうと、子どもは悲しむことが悪いことだと思ってしまうおそれがあります。一緒に泣いたり、話したりして、悲しみを共有してください。子どもの心に敏感に反応し、自由に悲しみや時には怒りを表現できる安全な居場所をつくる、そして共に死を悼むことがペットロスのサポートになるのです。
前のページは:ペットロスの悲嘆(グリーフ)の心理過程
次のページは:ペットロスのその先に